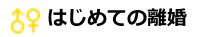離婚後の生活費を具体的にシュミレーションしてみる

子連れ離婚して母子家庭になったら、最も心配なのは離婚した後の生活費ですよね。
やっぱり、自分一人で子育てをしていく離婚後の生活のことを考えると、一番不安なのはお金のことです。
なんとなく漠然と『離婚したら生活がきつそう』と思っているだけだと、『離婚したいけどできない!』って思ってしまいます。
離婚したいと思っているけど、離婚後の母子家庭の生活費が…
母子家庭の世帯年収の平均は、240万円弱です。
手取りで計算すると、15万円前後。
生活は無理か!?
シングルマザー予備軍?の不安は、生活費の事が大半です。
でも実は、母+小学生2人なら、月13万円を稼げば生活できます。
実際に母子家庭になってから、生活費にいくら必要か、具体的にシュミレーションしておくと、漠然と思って怯えているより覚悟が決まるはずです。
なんとなく悩んでいる方に、具体的な手当などを含めて、生活費のシュミレーションをすれば、離婚した後でも大丈夫か判断ができます。
ここでは、離婚してからの母子家庭で少しでも経済的に安心できる制度や支援、そして養育費を確実にもらえる方法もあわせて紹介します。
離婚前に母子家庭のシュミレーションができれば第一段階クリア
離婚前は、
『離婚したいけど、母子家庭になったら経済的にきつそう…』
と、離婚をためらってしまう瞬間がありますよね。
でも、実際にそういう風に離婚前に、経済的に難しい~って考えられる人は、まだいい方です。
問題は、その場の感情で離婚してしまう人です!
結婚には勢いが必要だけど、経済的なことはとても大事で、離婚は勢いでしちゃダメです。

夫婦二人で、子供がいなければ勢いで離婚してもいいですよね。

子供がいなければ、「さようなら」って言ってすぐに、それぞれが別の人生に戻ればいいですからね。
夫婦二人だとしても、少しは悔しい思いはあるでしょうけど…
生活するためには、仕事+住む場所 のことを考える必要があります。
子供がいるのに、離婚してからその後の生活についてきちんと考えないと、即座に貧困母子家庭です。
離婚前に母子家庭のシュミレーションができれば、まずは、第一段階クリアです。
母子家庭の平均年収
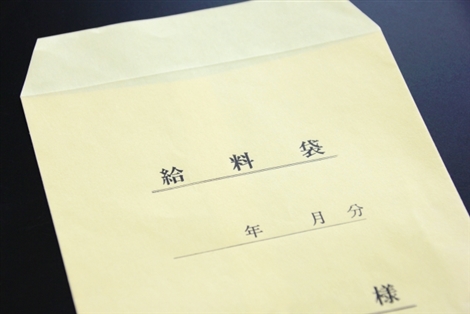
平成28年の調査での母子家庭の平均所得は348万円です(児童扶養手当等や同居する祖父母の収入も含まれます)。
(平成23年の調査では252万円)
世帯年収だと、母子世帯で243万円、父子世帯で420万円です。
(少し前ですが、厚生労働省の2017年12月に発表した平成28年度の調査結果(「平成28年度 全国ひとり親世帯等調査」)
これは、一般家庭の半分以下の水準です。
(子どもがいる世帯の平均年収は約707万円)
母子家庭の母親で働いている人は85%。
そのおよそ半数が臨時やパート勤務で正社員は約42%と雇用状況も不安定な状態です。
まだ調査はされていませんが、令和の時代になって世界中で蔓延した感染症の影響で、さらに平均収入が減ってしまっているかもしれません。
働きやすくする制度もある
母子家庭の厳しい経済状況に対しては、政府は平成16年度から特に力を入れて母親の就業支援など、母子家庭の自立を支援する政策に力を入れ始めました。
たとえば、ハローワーク経由での職業訓練を受けるときのお金です。
→母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金事業の実施について(厚生労働省のサイト)
職業訓練を受けて資格を取るなど、就労へ向けてひとり親が自分に投資するためのものです。
ざっくり言えば手に職をつけるためのものですが、訓練校や学校に通う場合に、生活費がなくなる、となると意味ないですよね。
この制度では、学校の受講費用などをひとり親の場合6割負担してくれる(一般の方は2割)んです。
ただ、終了後に6割を支払ってくれるものなので、立て替えしておくのが大変かもです。
シングルマザーが仕事して稼ぐべき金額

一方で、児童扶養手当の受給資格を厳しくする政策もとっています。

シングルマザーにとって、母子手当(児童扶養手当)がないと厳しいですね。

数字だけを見ると、小さな子供をつれての離婚には、かなり厳しい現実が待っているような気がしますよね。
数字だけを見ると、小さな子供をつれての離婚には、かなり厳しい現実が待っているような気がしますよね。
たしかに、無事に離婚できたとしても、子供を育てるにはお金がかかります。
でも、手当てがないからといって、それほど悲観して稼ぎまくる必要はありません。
自分のキャリアのためにも、少ない給料でもいいんです。
とにかく短時間でもいいので 「仕事をする」 ことです。
入ってくる収入を増やすことですね。

シングルマザーになると、手当がたくさんあるから大丈夫っていう話も聞いたことがありますけど...

確かに、母子家庭の手当としての収入はありますが、子供を抱えて、手当だけで生活というのは限界がありますよね。
少しでもいいので仕事をするというのは、最低限の生活をする上で必要なことだと考えていた方がいいです。
離婚したらどれくらい稼ぐ必要があるのか、収入と支出をザックリとシュミレーションして計算すれば、不安は少しは解消されます。
離婚後に働いて稼ぐ額は、母+小学生子供2人なら、月に130,000円の手取りがあればOKです。
離婚後の生活支援制度
離婚して母子家庭の生活が経済的にできるレベルなのかは、それぞれの家庭の状況によって違います。
シュミレーションしてみたものの、離婚したら、実際に生活費に困ったときや、役所の福祉課や保護課などに相談に行きましょう。
離婚後に働いて収入を確保することも、もちろん大事です。
でも、離婚して生活に困窮したとき、とくに子供を持って路頭に迷いそうになったとき、誰かの助けを求めたくなるのは当然のことです。
そんなときに、多くの人が公的支援制度を思い浮かべます。
たとえば、離婚して
- 実家には帰れない。
- アパート借りられない
など、どうしよう…ってなったとき
そういうときは、シングルマザーだったりしたら、母子寮などを案内してもらえることもあります。
自分から申請する制度が多い
手当や制度はどれも、自分から申請しないと利用できない制度が多いので、条件や資格などを調べて利用しましょう。
こういった離婚後の公的支援で、どこまで生活できるか、と考えるとかなり不安に感じてしまう人も意外と多いんですね。

生活支援の制度などは、相談しなければわからないこともあるんですね。

手続きもせず、役所にも行かず、自分一人で抱え込んでボロボロになる必要なんてないですよ。
母子家庭になった
↓自治体や周りが「かわいそう」と手を差し伸べてくれる
↓
公的支援の制度が受けられる
母子家庭になって、生活費が足りなさそうに見えても、自分から申請しないと、公的支援の制度は受けられないんですね。
たしかに、経済的支援はあくまでも一時的なものですし、資金の貸し付けなどでも、結局は保証人が必要だったり、審査が厳しかったりします。
実際には受けられないという人もたくさんいます。
とにかく自分で動いてみないとわからないことが多いですね。
一見、めんどうそうな手続きですが、かなり優遇されている公的支援制度が多くあります。
母子家庭が利用できる公的支援制度の例
母子家庭が利用できる公的支援制度は、母子家庭を援助する制度は多いけど自分で申請する必要ある、ということです。
母子家庭(父子家庭)の優遇制度としては以下のようなものがあります。
- 児童扶養手当
18歳未満の子供の(一定の障害がある場合は20歳未満)がいる母子家庭に児童扶養手当支給の制度があります。
父母等の離婚によって、片親と生計を同じくしていない児童を養育している親または監護者に条件を満たせば支給されます。
- 一人親家庭等医療助成制度
18歳未満の児童を扶養している一人親家庭の母または父およびその児童または父母のいない18歳未満の児童は、
医療費の自己負担分と、入院時の食事療養にかかる医療費が無料になります。(所得制限があります) - 医療費助成制度
18歳未満の子供がいる一人親家庭の親と子供の医療費の自己負担の一部を自治体が助成してくれる制度です。
助成の額は自治体によって異なります。 - 所得税・住民税の控除
一人親家庭の親は、所得税・住民税の控除を受けることができます。
控除の額は所得税で270,000円。住民税で260,000円です。 - 税金・国民年金の軽減
確定申告すれば所得税、住民税、国民年金の保険料が軽減されます。
国民年金の第一号被保険者について、収入がなく保険料が収められない場合や、生活保護を受けている場合などに保険料が免除される制度です。 - 水道料金の免除
児童福祉手当・生活保護を受けている家庭は、水道料金の基本料金と下水道料金の一部(一ヶ月8立方メートル以下)が免除されます。 - ホームヘルプサービス
一人親家庭の親が病気やけがで日常生活に困ったときに、一時的にホームヘルパーを派遣する制度です。
派遣の対象は市区町村によって異なります。 - JR定期券の割引
児童福祉手当、生活保護を受けている家庭の世帯員のうち一人を対象に、JR定期券の割引が受けられます。
自治体によってはバスや地下鉄の無料券があるところもあります。 - 受験生チャレンジ支援貸付事業
高校や大学受験をする際に必要な学習塾や通信教育、受験料を貸与する制度です。
一定の収入以下の家庭が対象で、貸与対象となる学校に合格した場合、返還が免除されます。 - 母子家庭等緊急支援擁護資金貸付
母子家庭等に対して、緊急に必要とする資金の貸付を行うことによって生活の安定と自立を図る制度です。 - 母子福祉センター
無料または低額な料金で、母子家庭・寡婦などに対して、各種の相談に応じるとともに、生活相談や生業の指導を行うなど、
母子家庭・寡婦などの福祉のための便宜を総合的に供与する施設 - 母子生活支援施設
母子家庭の母と子をともに保護して、入居者の自立の促進のため生活・住宅・教育・就職その他について支援する施設 - 生活保護
日本国憲法第25条に規定する理念(生存権)に基づいて、国が生活に困窮するすべての国民に対して、祖ノン旧の程度に応じた必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長する制度です。
離婚後の住居を考えるにあたっては、転居先の支援制度について調べて比較しましょう。
離婚前って、とにかく離婚したい気持ちがいっぱいですからね。
国や自治体は、子育て支援生活、就業支援、養育費確保支援、経済的支援の4つの柱のもとで、
一人親家庭を支援するさまざまな公的援助制度を設けています。
シングルマザーのシュミレーションに、知らなかった、わからない、と情報不足にならないでできる限りの制度を利用すれば、生活費でビクビクする必要はありません。
養育費は確実に決めておくべき
離婚時に未成年の子どもがいたら、確実に養育費の条件を決めておくべきです。
養育費はたいてい、通常「子供が成年になるまで継続的に毎月支払う」という約束をしていることが多いものです。
しかし、養育費の取り決めをして最後まで支払いされた人は2割にも満たない統計が出ています。
8割の人はあきらめと泣き寝入りをしているのです。
家庭裁判所でも、「養育費請求調停」という調停もあります。
→養育費請求調停(裁判所のサイトへ)
ただ、DVを受けていて離婚したとか、もう元夫の顔なんかみたくもない、連絡をこっちからとるのも嫌だ、ということの方が多いです。
養育費は子供にとっての権利で大事なお金です。
親の自分が泣き寝入りするのは子供への約束も自分が破っていることになるのです。
離婚前には、今の状態でどれくらいあるのかを把握して、養育費を捻出することを考えましょう。
離婚した後の母子家庭の生活(まとめとアドバイス)
離婚がきっかけとなって、貧困になった母子家庭って増えているんですね。
母子家庭になった家庭は、80%程度が離婚です(他は「死別(7.5%)」「未婚の母(7%程度)」)。
母子家庭になることが予想されるなら、本来は、お金の準備だけはしておくべきなんです。
離婚がきっかけになって「インターネットカフェ難民」「ハンバーガー難民」など、24時間営業のお店に寝泊まりすることになった人もたくさんいます。
子供がいたら、なかなかそんな生活は本当はできないですよね。
一定の住所がないままでは働くこともできないので、仕事に就くこともできなくなってしまうんです。
幼い子供がいるシングルマザーは、夜間保育園も充実してきています。
離婚前にある程度でいいので調べておけば、子供を長時間預けることができないために収入に限界があった人もよりも効率のいい仕事に就けるようになりますよ。