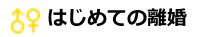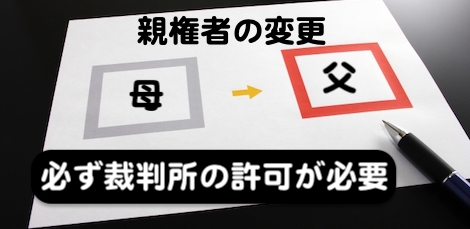家庭裁判所家裁が親権を決める基準はクール
離婚することは決めた、
でも未成年の子供がいる。
そこで、離婚届を出そうとするときにもめるのは、たいてい親権問題です。
日本では離婚した後に、親としての権利を行使する親権者を、父親か母親のどちらかを決めなければならないんですね。
離婚での子供の親権、いわゆる「親権者」を決めるのは、まずは当事者の協議、話し合いで決めることが基本なんですね。
本当は、子供の生活、福祉を考えて決めることが大切なんですけど、
親のエゴや離婚の際の意地の張り合いなどで決めようとしていることがほとんどだったりします。
だから、どうしても、離婚するときに子供の親権が決まらなければ、家庭裁判所で調停→離婚訴訟をすることになります。
調停や離婚訴訟の際には、家庭裁判所が、どちらが親権者としてふさわしいか判断するのですが、その基準はかなりクールです。
子供の親権が決まらない時に、家庭裁判所家裁が親権を決める方法を紹介します。
話し合いで親権者が決まらない場合は家庭裁判所が親権者指定をする

離婚することになって、両者とも冷静には離婚条件を話し合ったんです。
お金の事でもあんまりもめることなく、慰謝料と財産分与の金額も決まりました。
ところが
子供の親権者だけが決まらない!
困ってしまっているんです。

離婚届には、親権者となる父親か母親のどちらかの名前を記載しなければならないですからね。
この親権者をどちらにするかの話し合いができないと離婚届が出せず離婚することができません。
親のどちらも親権がほしい、またどちらの親も親権はいらない、ということもありますよね。
もし、決まらなければ家庭裁判所へ親権者指定の調停を申し立てます。
家庭裁判所で子供の親権を判断することになると、ほぼマニュアルどおりに決定されます。
つまり、子どもの年齢によって親権が決まってしまうんですね。
母親が優先の傾向がある
たとえば、特別な事情がない限りは、乳幼児であれば、母親が優先されています。

離婚の原因が母親の浮気(不貞)であっても、母親を親権者に指定することもあるんですね。
年齢別に親権者が決まる傾向があります。
0歳から10歳
衣食住全般にわたって子供の面倒を見なければならないので、母親が親権者になる例が多くなっています。
10歳から15歳
子供の精神的、肉体的な発育状況によっては、子供の意思を尊重するとの取り扱いがなされています。
15歳から20歳
子供が自分で判断できるので、原則として意思を尊重します。
満15歳以上なっているときは、家庭裁判所が子供の意見を聞かなければならないことになっています。
20歳以上
20歳をすぎると親権者の指定の必要はありません。
マニュアル通りだけど親権者の判断基準は一律ではない
親権では一般的にたいていの場合は、「働いている」「実家の協力が得られる」などがあれば、たいてい母親が親権をとります。

親権を家庭裁判所で決める場合、ほとんどが母親、ということを聞いたことがあります。

確かに、母親が親権と持つことが多いです。
でも、あくまで一般的な場合で、必ず母親が親権を持つ、ということではありません。
裁判所が子供の親権を決める一番のポイントは、子供の幸せです。
その他にも親権の判断基準があって一律ではないんですね。
親権を決めるにあたっての父母の側の基準
家庭裁判所が「親権者としてふさわしい親」の判断基準に、以下のようなものがあると考えられています。
- 子供の監護実績が多い経済的に安定している身体的・精神的に健全である
- 今後の子育ての計画がしっかりしている
- 今までの監護で子供の成長に悪影響を与えていない子供が両親の愛情を感じられるように、適切な面会交流をする意思がある
具体的には、次のような内容です。
- 心身の状態
- 生活態度
- 監護能力
- 精神的・経済的家庭環境
- 住居
- 教育環境
- 子供に対する愛情の度合い
- 従来の監護状況
- 監護補助者がいるか
などです。
裁判所が親権を決めるときに、親の基準として、子供に対する態度も重要になっているんですね。
試行的面会交流を裁判所がする
実際には、親権者を決める前には、試行的面会交流ということを行うことがあります。
夫婦の別居期間が長くなっていて、その間に一度も子供との面会交流が行われなかった場合とか、一方の親が面会交流に反対している場合に、家庭裁判所で行われるんですね。
例えば、
- 子供に対する虐待がないか
ということ。
虐待があって幸せになれないので、もちろんですよね。
さらに、
- 一方がもう片方の親の悪口を子供に吹き込んでいるか
これも、長い別居機関の間に、一緒に住んでいない相手の悪口を子供に洗脳するようなものですからね。
- 両親の間で子供が板挟みになってしまうような行わないか
具体的には、子供がもう片方の親のもとに行かないように、面会時に子供の目の前で泣いたりするような行為ですね。
長い別居期間中に子供に会っていない方は、久々に会うと、感極まって泣いてしまうかもしれません。
でも、裁判所ではこの行為は、子供を板挟みさせた親権者としてふさわしくないと判断される可能性があるんですね。
親権を決めるにあたっての子供の側の事情
- 年齢
- 性別
- 心身の発育状況
- 従来の環境への適応状況
- 環境の変化への適応性
- 父母との結びつき
- 子供の意向
などです。
子供は成長していくものですが、離婚の時の子供の年齢と親権者のバランスを考えることは避けられません。
実際に子どもが今、どんな状況にいるか、というのも家庭裁判所が離婚で子供の親権を決める際の判断材料になっています。
子供の現在の生活環境を維持するために、育児の放棄や虐待などの問題がない限り、実際に子供と生活し面倒をみている親を優先します。
だから、離婚前の別居を考えていて、親権者になりたいのであれば、子供を連れて出た方がいい、
と言われているのも、実際に子供を面倒をみている理由になるからなんですね。
このことを知っていて、ほとんど子どもを連れ去り状態で連れて行って別居してしまう親がいて、社会問題にもなっています。
現在の裁判所が親権者を決める傾向
いまのところ、裁判所で親権を決めるときは、マニュアルどおりに実際に一緒に生活をしている方、となっているんですね。
親権者となる親が心身ともに健康であること、子供と接する時間が多いことも判断材料の一つです。
これが、子供が満15歳以上であれば、裁判所は子供の意思を聞かなければならないことになっています。
満15歳未満であっても、子供の発達状況によっては本人の意思が尊重されます。
不貞行為やDVなどの有責配偶者でも、そのことを理由に親権者になれないわけではありませんが、
その内容によっては、性格や人柄が反映されていることも多いので、親権を得るのは難しいと考えられます。
経済力 も配慮するべきなのですが、
実際に養育しない方の親が養育費を支払うことによって解決できるので、必ずしも親権者決定の要素にはならないんです。
こういった考え方で家庭裁判所は親権者を決める傾向にあるので、
夫がサラリーマンで妻がパートや専業主婦など、妻の方が経済力がなくても、妻の方に親権をもっていく傾向にあるんです。
親権者の決定は、子供の利益や福祉を基準にして判断するべきものという考え方なんです。
どちらの親を親権者と定めれば子供にとって利益があって、幸せか、ということです。
これらの基準は、調停や審判、裁判などの第三者が決定する場合にも、考慮のもとになっています。
調停で親権者が決まらなかったその後
話し合いで親権が決まらないときは、調停や離婚訴訟で家裁が判断することになります。
審判
その調停を申し立ててもそれが不成立であれば、手続きは審判に移行します。
審判については、調停前置主義(裁判の前には調停をしなければならないこと)はないので、いきなり審判申し立てをしてもかまわないんです。
この審判は、協議で離婚することは決まったけれど、親権についての協議だけができない場合のことです。
もし、一方が、自分が親権者にならないのは不本意だから離婚にも応じない、
というのであれば、審判で定めることはできません。
離婚そのものは調停・訴訟事項なので審判による事項ではないからです。
ただ、家庭裁判所も「調停に代わる審判」としての審判を下すことができるのですが、
これは当事者から2週間以内に異議申し立てがあれば効力はなくなり、訴訟をするほかはなくなります。
離婚裁判
離婚裁判をすると、裁判所が夫婦の一方を親権者と定められます。
家庭裁判所では夫婦双方のさまざまな事情を考慮して親権者を定めます。
ここでは、子供が15歳以上の場合には、裁判所は子供の意見を聞いた上で、親権者を定めることになっています。
子供がどう思っているか、が重要視されるんですね。
監護者が決まらない場合
監護者についても、まずは協議です。
協議で決まらない場合には、家庭裁判所に子の監護者指定の調停を申し立てます。
審判では家庭裁判所が職権で手続きを進め、家庭裁判所調査官の事実調査があります。
子供の家庭環境が調べられ、当事者の審理が行われた後、審判が下されます。
離婚で子供の親権が決まらない時に家庭裁判所が決める方法(まとめとアドバイス)
離婚することは決めたけど、親権が決まらないばかりに、調停・離婚訴訟まで進んでしまうこともあります。
離婚訴訟に進んでしまうと、家庭裁判所が決めるクールな判断方法は、ほぼほぼ子供の年齢で決まってしまうことが多いんですね。
離婚を決めたらまずは財産をチェック
離婚のときに問題になるのは、親権・財産のことがほとんどです。
財産の問題がクリアになれば、未成年の子供がいるなら親権者をどちらかにするか、です。
たいていの場合、離婚を言い出した後は、夫婦二人が冷静に話し合うことが難しくなります。
「離婚」と言い出したその後は、話し合いというコミュニケーションを夫婦ですることは、もう手遅れだったりします。
もしかしたら財産のことについてこじれて「親権」すらも話し合えないとも多いです。
だから、家の財産チェックを先にしておいた方がいいです。
もしご自宅などの不動産を所有しているのなら、最終的に離婚したとなるとお金の問題は、財産分与で清算、という方法をとります。
法律上、財産分与は、婚姻期間中に築いた財産を夫2分の1、妻2分の1の割合で分け合うのが原則です。
その際にはご自宅の価値がどれくらいなのかを把握しておくことは必要です。住宅ローンはその価格から差し引きます。
→住宅ローンがあるときに財産があるかのチェック方法