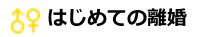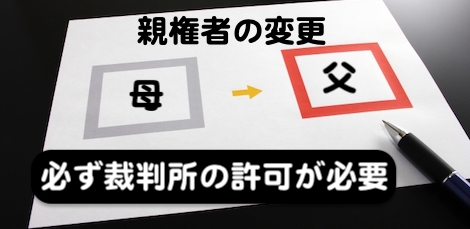離婚する時、親権を決めるにあたって、
長男は跡取りだから...
こう宣言して親権を主張するのって、戦前の家制度を思い出しますよね。
そもそも「跡取りだから親権を」というような決め方ができるのでしょうか。
「跡取り」は親のエゴな考えで親権の条件にはできません
離婚裁判になると「子供を跡取りにしたいから親権を」という理由はまず通りません。
- たった一人の男の子だから
- 長男は家を継ぐ子どもだから
こんな風に言われても、今の時代、家族制度が重要な意味を持たないし、ただの親のエゴですからね。
でも、どうしても子どもを跡取りにしたいのなら、協議離婚ができるうちに決着するしかありません。
この記事では、親権と跡取りには関係性が全くないだけなく、今の離婚事情には合わない理由を紹介します。
跡取り息子は親権の決定要素にならない
そもそも、愛だの恋だのの概念と一緒に、西洋文化が入ってくるまでは、結婚は「家と家」の結びつきだったんですよね。
- 家系を絶やさない
- 家業を継がせる
- 女にとっては生活のため
- 男にとっては子を産ませるため
そういうものだったんです。
今は、恋愛結婚が主流ですよね。
でも、結婚したら…の先にこの古い考え方に近い場合もありますよね。
その一つが離婚しても、息子を「跡取り」にしたいから親権をとりたい、という問題に発展してしまうんです。

離婚するのは決まったんですけど、子供を跡取り息子にしたい母の意向で 親権 を妻にするか自分のどちらかにするか問題になっているんです。
跡取り としての必要性は、離婚の際に親権者を決定するのに考慮されるのでしょうか?

少子化が進んでいる現代の社会では、子供が父方・母方の祖父母にとって唯一の孫であることも多いですからね。
とくに子供が男子の場合「家」を継がせたいから親権は譲れない、と主張がなされることはよくあるんです。
子どもに家を継がせる=家制度
これが古い民法です。
家制度は昭和22年の民法改正によって廃止されたので、そもそも親権者は子の福祉の観点から決定されるべきもので、「家」の都合で決せされるべきものではありません。
したがって、跡取りとしての必要性が親権の帰属に影響することはありません
親権と監護権をわけて離婚するなら

実際に育てる妻の方に監護権は譲るとして、 親権だけ はこちらのほうに、ってことはありえますか?

親権と跡継ぎが問題になると、跡取りにしたいので監護権は譲るが親権は譲れない、との主張がされる場合もあります。
でも、子の福祉の観点からすれば、親権と監護権が分かれてしまうことは避けるべきといわれています。
親権と監護権を分けてしまうと、子どものためにならないことがあります。
たとえば子供の財産を処分するときにもふだん面倒を見ていない親権者が決定することになるんですね。
親権問題でもめて、調停や訴訟にすすんだりすると、いわゆる跡取りのためだけに親権と監護権を分けて異なる決定を裁判所が行うことは通常はないです。
子どもの氏を変えないで離婚するなら

実際に離婚して 子供の名字 だけは変えないようにする、という方法はできますか?

できますが、子供の氏(苗字)をどうするかは、子ども自身か親権者が決定すべきことなので、そういう主張は合理的といえないでしょうね。
苗字を残したいとの意向から「子供の苗字を変えないと約束すれば親権は譲る」との主張がなされることもあります。
でも、子供の方からすると年齢によっては、名前が変わることにシビアな子もいるんですよね。
そもそも『子供を跡継ぎにしたい』という親のエゴで名前が変わるわけです。
離婚体験談の中にも、子供が名字を変えることに抵抗して、結局再婚できない例もありました。
→子連れ再婚してから戸籍「姓」に反対され幸せのため再び離婚することに【離婚体験談】
親権と跡取りとは関係性なし
- 親権=子供のための権利
- 跡取り=親のエゴ
親権は、法律上は、成年に達しない子を監護、教育し、その財産を管理するため、
父母に与えられた身分上及び財産上の権利義務の総称のことで、
未成年の子に対し、親権を行うものを親権者と言います。
親権の内容は二つに分かれていて、
一つは「身上監護権」と言って、子供を現実的に育てて面倒を見る権利です。
もう一つは、「財産管理権」で、子供が持っている財産を判断能力が不十分な子供にかわって管理したり、未成年者が一人ではできない法的な契約などを代わりに行う権利です。
基本的なイメージとして、親権があればその子供と一緒に生活をしてくことができて、子供に関することについて全面的に決める権利があると考えていいです。
つまり、親権は子供のこれからのことが中心に考えた制度です。
一方で、跡取りというと、まさに親の恣意、望むところ、ですよね。
まったく関係がないわけです。
家の存続という理由での親権の主張は難しい

よく、芸能人の歌舞伎役者が離婚する際に、伝統を重んじるために、長男を親権にしたい、という報道がされていることもありますね。
でも、法律的な「親権」をこのような観点からみると、仮に、子供が歌舞伎役者の後継で、幼少の頃から英才教育を受けていた。
そのため、家の存続のために父親に親権を残さなければならない、と主張しても、裁判所はそのような父親の主張を認めることはないでしょう。
せっかく教育した後継をどうしても残しておきたい、という理由はあくまでも父親の家の事情であって、子供から見たら親権を父親にする理由にするには乏しいと言えるからです。
自分の子供の親権を取りたいという思いは、芸能人でも一般人でも変わりありません。
いざという時に後悔しないように、どのような基準で親権が決められているのか知っておくといいです。
→離婚で子供の親権が話し合いで決まらない!家裁はどうやって決める?
祭祀継承と名前の関係はどうなの?
「
祭祀継承
」
とは、ざっくり言えば、仏壇やお墓など神仏祖先をまつるためのものを受け継いでいくことです。
いかにもむかしの家族制度にあった行事、というイメージですよね。
今の民法にもまだ規定があるのですが、祭祀承継者とは、系譜、祭具及び墳墓等の祭祀財産を承継する者です(民法897条)。
「系譜」とは、いままでの家長を中心に祖先伝来の家計をあらわしたものです。
いかにも古めかしい規定ですが、
- 祭祀継承者である子どもと父母の実家とで氏(苗字)が異なることが問題になるのではないか
- 離婚に際して婚氏継承すると実家の墓に入れないのではないか
と考える人もいます。
そう考えたとしても、苗字と祭祀は基本的に関係がないので問題はないです。
どうしても、というならお寺・教会などと相談してみるといいです。
また、「墓守」がいない場合の墓の管理についても不安を持つ方も多いのですが、最近ではいわゆる「墓じまい」の手続きも一般的になってきました。
現在の墓は廃墓して、永代供養墓等、他の墓に改葬することが多いようです。
具体的な手続きは墓地管理者に確認するしかないんですね。
離婚するとき跡取りとしての親権を約束できるの?(まとめとアドバイス)
「跡取りのために親権」は裁判では通用しない
跡取り息子だというだけでは、親権を決める要素にはなりません。
親のエゴで
- 親権と監護権をわける
- 子どもの氏を変えないで離婚する
という方法もありますが、どうしても、跡取り息子にしたいのなら、協議離婚のうちに決めるしかありません。
親権と跡取りとは関係性がないので、家の存続という理由で親権の主張するのは、離婚裁判では理由にならないからです。
離婚する時になってまで、子どもを家の「跡取り」という別の制度の道具になるなんて、夫婦生活って一体なんだったんだろう?って思いますよね。
- 夫婦のこと
- 親戚関係
- 嫁姑問題
今まで過ごしてきた時間を振り返って、離婚のことで悩んでいたり知りたいことがあれば相談してみるといいですよ。
→
財産分与はご自宅を売却しなくてもチェックが必要
財産分与を計算するとき、ご自宅は売らなくても査定額が計算の基準になります。
お金の計算は知っておくと有利になりますよ。